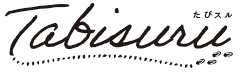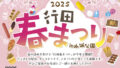満る岡(まるおか)
六代目オーナー 市原 祥 さん
料理長 荒川 𠮷則 さん
事業内容
うなぎを中心とした川魚料理を提供する和食店の運営
プロフィール
市原 祥(ひろし)さん:昭和50年7月20日生まれ、行田生まれ行田育ち。妻と高校生の長男、小学生の長女の4人家族。大学卒業後、埼玉縣信用金庫に12年間勤務。その後、妻の実家である「満る岡」を継ぐため、13年前に転身。銀行員時代の経験を活かし、歴史ある老舗の暖簾を守っている。
荒川 𠮷則(よしのり)さん:鴻巣市出身。高校卒業後、料理の道へ進む。独学で調理師免許を取得し、焼肉店で肉の扱い方を学ぶ。その後、結婚式場で和食を担当し、うなぎ専門店2軒で修業を積む。さらに寿司懐石料理店で技術を磨き、「満る岡」に入店。入店から約20年、うなぎ職人として腕を振るう。

——創業からの歴史について教えてください。
市原さん:当店は1875年(明治8年)に創業し、今年でちょうど150年になります。私は6代目です。創業当初は、うなぎを中心とした川魚料理を提供する料理店として営業しながら、酒屋も兼ねていました。しかし戦後、酒屋の免許制度が導入されたのを機に、料理屋一本でやっていくことになりました。酒屋を営んでいた時代の名残として、今も店先や店内には酒の甕(かめ)や瓶が置かれ、当時の面影を伝えています。

また、当店は田山花袋の小説『田舎教師』にも登場しており、長い歴史の中で多くの人に親しまれてきました。
——昔は「どかどか」という愛称で呼ばれていたと聞きましたが?
市原さん:はい。お店のすぐ横に川が流れていて、昔はそこに堰がありました。飛脚や旅人の休む場所になっていたそうです。その堰から水が「どかどか」と流れる音がしていたことから、その愛称がついたと聞いています。今でもご年配の方には「どかどか」と呼ばれることがありますね。
——昔から、川魚が獲れたのでしょうか?
市原さん:そうですね。やはり利根川と荒川に挟まれた地域なので、川魚文化は行田市をはじめ、埼玉県北部に根付いていると思います。埼玉県全体でも、浦和がうなぎの蒲焼の発祥の地の一つとされているように、川魚を食べる文化が昔からありました。当店でも、うなぎだけでなく、鯉の洗いや川魚の料理を提供してきた歴史があります。
——お店の建物も歴史を感じますね!
市原さん:2001年に大規模な改装を行いました。それまで予約制の料亭だったお店にホール席を作り、より多くのお客様にお食事を楽しんでいただけるようにしました。改装の際は、築100年以上の歴史ある梁をそのまま残し、昔の風情を大切にした造りとなっています。2001年には埼玉県の景観賞、2005年には行田市の景観賞を受賞しました。


ホール席は約20名様が入れます。宴会場は70~80名様を収容できる大部屋があり、ほかにも30名様ほどの中部屋や、10名様以下の小部屋もいくつかご用意しています。その後、4年前には宴会場の老朽化に伴い改装を行い、耐震対策も実施しました。また、駐車場も整備し、30台駐車可能になりました。
——市原さんが銀行員からうなぎ店のオーナーになられたきっかけは?
市原さん:大学卒業後、埼玉縣信用金庫に12年間勤務していました。一生の仕事と思って銀行員をやっていましたが、同級生だった妻との結婚を機に、妻の実家である「満る岡」を継ぐことを考えるようになり、とても悩みましたが思い切って家業に入りました。まったくの異業種への転身でしたので、経営面では銀行員時代の経験を活かせる部分もありましたが、料理に関しては素人でした。板前さんたちに教わりながら、少しずつ理解を深めてきました。もう13年になりますが、今ではこの道に進んでよかったと感じています。

——うなぎ料理へのこだわりを教えてください。
荒川さん:ここでは、生からうなぎを裂いて、白焼きして、蒸して、本焼きしてお客様に提供しています。その工程を、ひとつひとつ丁寧にやることを大事にしています。うなぎによって蒸し時間や焼き加減を見極めながら、一番美味しい状態でお客様にお出しできるよう心がけています。
また、タレは創業以来、継ぎ足しを繰り返しているもので、甘さ控えめなのが特徴です。焼くたびにうなぎをタレにくぐらせることで、タレの中にうなぎの旨味が凝縮され、より深い味わいが生まれます。長い間、受け継がれてきた味を守り続けています。


——うなぎの焼き方は地方で違うと聞きましたが?
荒川さん:関東では背開きにして蒸してから焼くので、ふっくらとした仕上がりになります。一方、関西では腹開きにして蒸さずにそのまま焼くため、皮がパリッとした仕上がりになります。脂の強さは関西のほうが際立つかもしれませんね。
——荒川さんの料理に対する信条はありますか?
荒川さん:昔の職人の世界では、言葉で細かく教えてもらえることは少なく、親方や先輩の技を見て覚えるのが基本でした。とにかく見て、技を盗むつもりで必死に学んできました。その中で、道具の大切さを実感しましたね。特に包丁の切れ味は料理の仕上がりに直結するので、常に砥いで良い状態を保つようにしています。また、自分の手になじむ包丁を選び、納得したものを長く愛用しています。

——うなぎは夏のイメージがありますが、実際に美味しい時期はいつですか?
市原さん:昔から「うなぎは冬が美味しい」と言われています。寒くなる前に栄養を蓄えるので、秋の終わりから冬の始めにかけて脂がのってくるんです。
荒川さん:冬は身がふっくらしていますよね。逆に夏場は身が薄くなる印象です。でも、季節に応じた調理をすることで、どの時期でも美味しく召し上がっていただけるよう工夫しています。
——どのようなお客様が多いですか?
市原さん:冠婚葬祭やお祝いの席、会社の会食などでご利用いただくことが多いですね。一般のお客様にも、うなぎを楽しんでいただいております。
——人気メニューは?
市原さん:やはり「うな重・特」が一番人気ですね。他には、「鯉の洗い」もおすすめです。

——現在の課題はありますか?
市原さん:うなぎの価格高騰に加え、光熱費や仕入れのコストが上昇しているため、利益率の確保が難しくなっています。また、人手不足も深刻ですね。
——お店の雰囲気作りで意識されていることは?
市原さん:せっかくご縁があって働いてくれているスタッフには、ただ仕事をこなすだけでなく、ここでの経験が将来につながるようなものになってほしいと考えています。接客の仕方や調理技術など、それぞれが学べることを増やし、『ここで働いてよかった』と思える職場づくりを大切にしています。また、仕事以外でも悩みを相談しやすい環境を作るため、食事会を開いたりしています。

——今後の展望を教えてください。
荒川さん:うなぎは調理に時間がかかるので、お客様をお待たせしてしまうこともありますが、「待ってよかった」と思っていただける料理を提供したいです。今後も精進します。
市原さん:150年の歴史を守りつつ、時代に合わせた店作りを進めていきたいですね。若い方にも気軽に来ていただけるような工夫をしながら、伝統の味を守り続けたいです。


満る岡(まるおか)
行田市城西4-6-21
048-554-2263
営業時間:11:00〜14:30 / 17:00〜21:00
定休日:毎週月曜日夜の部・火曜日(祝祭日は営業)
https://maruoka-gyoda.com
https://twitter.com/maruoka720